執権北条氏(以下「北条氏」とします。)は平氏と言われていますが、平氏=秦氏と考えるのは早計で、平氏は元々は出雲族と言われています。
平氏が秦氏となったのは平清盛からであり、北条氏も同じ時代に登場していますので、秦氏に与したと考えても不思議ではありません。
平清盛が登場する辺りから源平合戦が激しくなったのも、源氏と平氏が出雲族と秦氏とに分かれてしまったためだったのです。
北条氏と言いますと、「源頼朝に早くから加担して、平氏を倒し鎌倉幕府を作るのに尽力した」、というのが一般的な認識です。
しかしながら北条氏は、源氏(源頼朝とその子供たち)を全て滅ぼしました。
源頼朝を殺し、鎌倉幕府二代将軍の源頼家(頼朝の嫡男)を殺し、鎌倉幕府三代将軍の源実朝(頼朝の次男)を殺して、かつ、源氏に近かった御家人たち(推測するに出雲族の連中)をことごとく殺し、鎌倉幕府を乗っ取ったのが北条氏です。
源氏は紛れもなく出雲族なので、その源氏を滅ぼしたということは、北条氏は秦氏であった可能性が考えられるわけです。
源頼朝に加担する前は、北条氏も平清盛の配下として東国で活動していたようですが、そのことはあくまでドラマなどでしか確認したことがなく、信憑性は疑われます。
平清盛に逆らった源頼朝に加担したということは、北条氏は元々は出雲族であったと考えた方が自然だと思います。
北条氏が秦氏だと仮定したら、源頼朝に加担するでしょうか。
しかも、北条氏が源頼朝に味方した当時、まだまだ平氏の力は強く、平清盛も健在でしたから、北条氏が秦氏であったとは考えにくいわけです。
私の推理としましては、北条氏は出雲族でありながら、源頼朝を殺す1190年代後半あたりから1220年代前半の承久の乱あたりまで秦氏に加担したのではないか、と思うのです。
つまり、北条時政と北条義時が秦氏に肩入れし出雲族である源氏を滅ぼしたのではないかと推理しました。
そして、北条泰時の時代になり再び出雲族として活動したのではないか、と推理します。
実際に承久の乱の後、間もなく北条義時は死んでいますし、その最期は病死とは伝えられているものの、暗殺の可能性も示唆されています。
北条氏内部で出雲族と秦氏に別れて争い、秦氏に与した義時を殺して出雲族に戻ったという推理です。
事実かどうかは定かではありませんが、北条政子(義時の姉)によって殺されたかのように描かれている作品もあるようですが、意外と事実である可能性も考えられます。
以下に、三つの画像をご紹介します。

この画像は、ウィキペディアで紹介されている北条時政のものですが、赤い服を着ているように見えますが、一方では青も使用されているので秦氏とも出雲族とも捉えることができます。

この画像は、ウィキペディアで紹介されている北条義時のものですが、来ている服はオレンジで赤寄りの色をメインに使用していますが、中身には青も使用されています。
中身は出雲族だけれども秦氏の仮面を被っている、という捉え方も出来なくはないですね。
2022年に放送されたNHK大河ドラマ「鎌倉殿の13人」は北条義時が主人公でしたが、画像検索をすると緑色の衣装が目立ちました。
緑色は藤原氏を示す色ですが、果たしてどうなのでしょうか。

この画像は、ウィキペディアで紹介されている北条泰時のものですが、鎧や衣装は青をメインとして描かれていますが、傘の様なものは赤で描かれています。
これらの画像から推測するに、やはり北条氏は出雲族ではあるけれども、時政と義時の時代に秦氏に与した可能性があり、泰時の時代に再び出雲族として活動したのではないでしょうか。
勿論、画像だけで判断できるものではありません。
では、出雲族である北条氏が秦氏に与した要因は何だったのでしょうか。
このことについては十分に調べる必要はありますが、おそらくは平清盛が秦氏として活動した時のように、秦氏の者(おそらくは西洋人で、ロスチャイルドの人物)が北条氏に接近し、一時的に秦氏に与するように促したのではないかと考えました。
要するに、秦氏に鞍替えした平氏を源氏が滅ぼしたわけですから、その恨みを晴らすために秦氏が北条氏を使って源氏を滅亡させた、ということです。
そうしますと、鎌倉時代に起きた大きな戦争の構図に整合性が取れるように感じるのです。
1221年 「承久の乱」 北条義時(秦氏)VS 後鳥羽上皇(出雲族) 1274年、1281年 「元寇」 北条時宗(出雲族)VS フビライハン(秦氏) 1331年 「元弘の乱」 北条高時(出雲族)VS 後醍醐天皇(秦氏) ※1324年に起きた「正中の変」も、北条VS後醍醐
実際に北条氏は、源頼朝が征夷大将軍に任命されて以降、急速に力を強めたのです。
たとえ源頼朝の親戚となったとはいえ、あまりにも不自然過ぎるほどの権力の持ちようです。
それこそ源頼家の舅となった比企氏こそ、北条氏との二大勢力となってもおかしくなかったはずなのにあっけなく北条氏に潰されました。
何者かの援助があったと考えても何ら不思議では無いということです。
それが秦氏(ロスチャイルド)だったという推理です。
少々余談ですが、北条氏は、鎌倉時代の後半には足利氏(出雲族)とも懇意にしています(実際に婚姻関係を結び親戚となっている)ので、やはり出雲族と考えた方が辻褄が合う感じがするのです。
そして北条氏が源氏を裏切ったように、足利氏が出雲族でありながら秦氏である後醍醐天皇に与して北条氏を倒したわけです。
しかも、承久の乱と同じように、足利尊氏(出雲族)と後醍醐天皇(秦氏)が激しく争うことになるわけです。
と同時に、足利氏に討たれた北条氏も後醍醐天皇と共に、足利尊氏に対して戦争を仕掛けています。(中先代の乱)
この辺りの構図も非常に共通項がある感じがしますので、私の推理も決して的外れでは無いことがご理解いただけるのではないでしょうか。
それでは話を鎌倉時代初期に戻して考察したいと思います。
まず、源頼朝の死についてですが、ウィキペディアを見ると、これまた幾つもの説が挙げられています。
ということは、世間としては、源頼朝の死の真相を知られたくない、ということでしょう。
私は、北条氏による暗殺(毒殺)の可能性が極めて高いと考えています。
では、以下にウィキペディアから抜粋してご紹介します。
死因
[編集]
各史料では、相模川橋供養の帰路に病を患ったことまでは一致しているが、その原因は定まっていない。『明月記』『愚管抄』『百錬抄』は「病死」、『猪隈関白記』は「飲水の病」、『吾妻鏡』は「落馬」、『承久記』は「水神に領せられ」、『保暦間記』は「源義経や安徳天皇らの亡霊を見て気を失い病に倒れた」と記している。これらを元に、頼朝の死因は現在でも多くの説が論じられている。死没の年月日については、それ以外の諸書が一致して伝えているため、疑問視する説は存在しない。
落馬説 建久9年(1198年)、重臣の稲毛重成が亡き妻のために相模川に橋をかけ、その橋の落成供養に出席した帰りの道中に頼朝が落馬したということが『吾妻鏡』に記されており、頼朝の死因として最も良く知られた説である。しかしその話が『吾妻鏡』に登場するのは、頼朝の死から13年も後のことであり、「その橋が壊れて地元民が困っていたが、頼朝の落馬から縁起が悪いとずっと放置されていた」という内容である。死去した当時の『吾妻鏡』には、橋供養から葬儀まで、頼朝の死に関する記載が全く無い。これについては、頼朝の最期が不名誉な内容であったため、徳川家康が「名将の恥になるようなことは載せるべきではない」として該当箇所を隠してしまったとする俗説があるが、『吾妻鏡』には徳川家以外に伝来する諸本もあり、事実ではない。また、『吾妻鏡』に記されているのは「頼朝が落馬してから間もなく亡くなったため縁起が悪い」ということなので、必ずしも落馬が原因で死亡したとは書かれていない。なお、死因と落馬の因果関係によって解釈は異なる。落馬は結果であるなら脳卒中など脳血管障害が事故の前に起きており、落馬自体が原因なら頭部外傷性の脳内出血を引き起こしたと考えられる[81]。落馬から死去まで17日あることから、脳卒中後の誤嚥性・沈下性肺炎の可能性もある。
糖尿病説 『猪隈関白記』の「飲水の病」とは水を欲しがる病であり糖尿病を指すとする。しかしそのような症状があったという記録はなく、可能性は低い[81]。そもそも糖尿病は直接の死因となる病気ではなく、合併症が死因となる病気である。仮に糖尿病による死だとしたら、当時の人間がそれが死因と認識して「飲水の病」と記録に残すとは考えにくい。
尿崩症説 落馬で脳の中枢神経を損傷し、抗利尿ホルモンの分泌に異常を来たして尿崩症を起こしたという説。この病気では尿の量が急増して水を大量に摂取する(=「飲水の病」)ようになり、血中のナトリウム濃度が低下するため、適切な治療法がない12世紀では死に至る可能性が高い[81]。
亡霊説 『保暦間記』に記されている。当時は亡霊や祟りが深く信じられている時代であり、信心深い頼朝には義経や安徳天皇の亡霊が見えたのであろうと言う。医学でいう意識障害のような失調症があったと捉えることもできる。ただし、「亡霊を見た」という記述をそのまま鵜呑みにするだけでは学説とは言えず、現代医学でいう所での疾患名が特定されないことには意味は無い。原因と結果は逆であり、何らかの病気で意識が混濁した頼朝が亡霊を見た可能性も否定できない。ただしそれは”死因”ではない。
溺死説 史料は「飲水の病」「相模川橋供養」「水神の祟り」「海上に現れた安徳天皇」など水を連想させる語が多く、溺れたことが死に繋がったのではと見る。また相模川河口付近は馬入川とも呼ばれており、頼朝の跨った馬が突然暴れて川に入り、落馬に至ったことに由来するとも伝わる。溺死説の場合、「飲水の病」は川に落ち溺れ、水を飲み過ぎたことを意味すると見る。だがいずれも根拠のない推測に過ぎない。
暗殺説 頼朝は子の源頼家や実朝と同じく何者かに暗殺されており、その事実を隠すべく『吾妻鏡』への記載を避けたとする。あるいは北条氏に水銀を飲まされて死んだとも言う(伊豆では水銀が産出されている)。だがいずれも全く根拠はない。
誤認殺傷説 愛人の所に夜這いに行く途中、不審者と間違われ斬り殺されたとする。これも全く根拠はなく、証拠以前に、斬り殺した人間、遭いに行く予定の愛人が誰か特定できないことには、学説として成り立たない。
※転載ここまで。
しかしよくもまあ、これほどまでに死因を作り出せるものですね。(笑)
これこそ、我々を真実から遠ざけようとするイルミナティ側の常套手段とも言えます。
これ以外にも、様々な説明の中で、「なんちゃら説」とか、不自然に多すぎると感じるのは私だけでしょうか。
しかも、上記にある暗殺説には「水銀」の存在が書かれてありますが、このことはイルミナティ側の失態に等しいと思うのですが、いかがでしょうか。
「根拠は無い。」と書いていますが、「いやいや、根拠十分ですよ」、と私は思いますが。(笑)
RAPT理論でも、悪魔崇拝者たちは古くから麻薬の代用として水銀を使用していた、と暴かれています。
庶民的な感覚で言いますと、源頼朝は北条政子の旦那、源頼家と源実朝は北条政子の実子、なので北条氏が殺すとは考えにくいでしょう。
しかしながら、何度も書いていますが、日本の歴史は悪魔崇拝者の歴史です。
悪魔崇拝者が自分の家族を殺すことなど朝飯前です。
従いまして、源頼朝を北条氏が暗殺したとしても何ら不自然さはありません。
更に、北条氏が将軍に準ずる執権という立場を得たのも、源頼朝の死後(正確には二代将軍源頼家の死後)でした。
北条氏は源頼朝の死後、梶原景時を殺し、比企能員(ひきよしかず)を殺し、二代将軍の源頼家を殺し、執権になりました。
梶原景時は源頼朝に重用されていましたので出雲族と思われます。
比企能員も源頼家の舅となっていますので、やはり出雲族と思われます。
このように、源頼朝が死んでからというもの、出雲族と考えられる人々をことごとく殺している様子から、1200年前後には北条氏は秦氏に与したのではないかと考えられます。
秦氏に与した北条氏が源頼朝を毒殺し、更に出雲族の有力者を殺害し、幕府を乗っ取ったということだと推理します。
次回は、三代将軍源実朝の死から承久の乱のあたりを考察したいと思います。
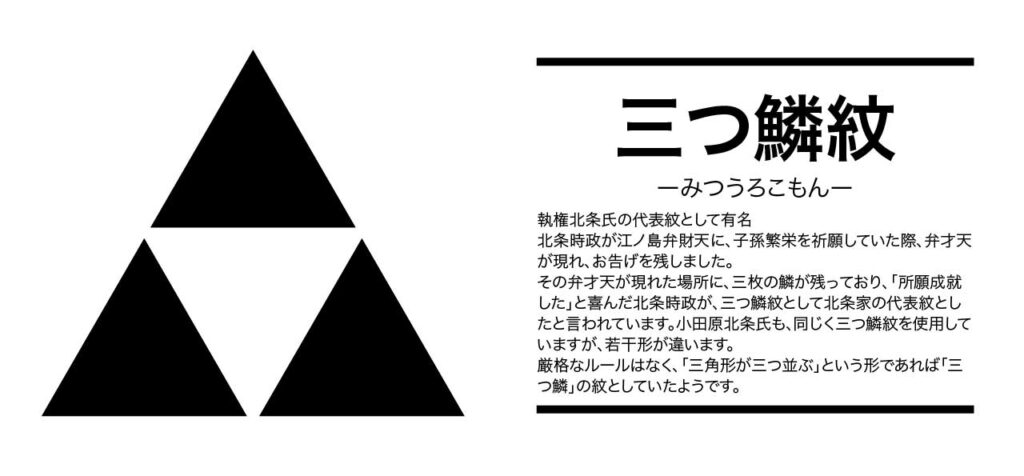


コメント